筋トレを終えた後、ストレッチやジョギング、ウォーキングなどの「クールダウン」を取り入れている方は多いでしょうか。
しかし、最近の研究では、アクティブ・クールダウン(ジョギングやウォーキング)には期待される効果がないことが示されています。
意外かもしれませんが、ジョギングよりもマッサージやストレッチの方が、筋トレ後の回復において最も効果的だとされています。
今回は、「筋トレ後のジョギング(有酸素運動)は本当に意味がないのか?」というテーマで、最新の研究結果を紹介します。
有酸素運動の常識が覆る理由
ジムでは、多くの人が筋トレ後にジョギングやウォーキングを行っていますが、実際にはアメリカのトレーナーの89%がクールダウンを推奨しています。
クールダウンには、大きく分けて2つのタイプがあります。
- アクティブ・クールダウン:ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動。
- パッシブ・クールダウン:マッサージやストレッチなどの柔軟体操。
これまで、アクティブ・クールダウン(有酸素運動)には疲労物質の減少や筋肉痛の軽減、心拍数の回復などの効果があるとされてきましたが、オランダ・マーストリヒト大学の研究によると、これらの効果は否定されているそう。
筋トレと有酸素運動の関係について
筋トレとジョギングなどの有酸素運動を組み合わせると、筋肉にどのような影響があるのでしょうか?
最近の研究では、筋トレの効果が減少する理由として「残留疲労」と「AMPKの活性化」という2つの要因が考えられています。
残留疲労とは?
ジョギングなどの持久力トレーニングを行うと、体のエネルギー源である筋グリコーゲンが減り、筋肉に小さな損傷が生じ、この状態を「残留疲労」と呼びます。
そんな残留疲労があると、筋トレをしても筋肉の『タイプⅡ線維(速筋)』を十分に使えなくなってしまいます。
力を出したり、速く動いたりするために重要な筋肉の1つであって、速筋ともいう。
筋力とパワーの増強
筋力やパワーを高めるためには、タイプⅡ線維を多く使うことが大切。
しかし、残留疲労があると、トレーニングのパフォーマンスが落ちてしまい、十分にタイプⅡ線維を動員できず、それが筋力やパワーを増やす効果を減少させる原因となります。
トレーニングの総負荷量
筋トレによる筋肥大(筋肉が大きくなること)の効果は、筋タンパク質の合成によって生じます。
この合成は、トレーニングの「総負荷量」によって決まります。
総負荷量とは、トレーニングの強度、回数、セット数を合わせたものであり、残留疲労があると十分な総負荷量を得られず、筋タンパク質の合成が促進されないため、筋肥大の効果が減少します。
AMPKとmTORの関係
さらに、分子生物学の観点からも、筋トレと有酸素運動の関係がわかってきています。
筋トレをすると「mTOR」という酵素が活性化され、筋タンパク質の合成が進みます。
しかし、ジョギングを続けると、体内の酸素が不足し、エネルギーを生み出すために「AMPK」という酵素が活性化されます。
AMPKはエネルギーを作るために糖の利用や脂肪の燃焼を助けますが、同時にmTORの働きを抑えてしまいます。
このAMPKによるmTORの抑制が、筋タンパク質の合成を妨げ、筋肥大の効果を減少させることが示唆されています。
ーーこれから減量始めるにあたって、どこから着手しますか?
引用先:http://x-plosion.jp/shout/x-plosion-e-yokokawanaotaka2/
横川 食事ですかね。トレーニング内容を変えるつもりはないし、有酸素運動をやるつもりもないので、食事の質を変えていくしかないので。インスタント食品とかジャンクなものを止めて、糖質類を抑えるだけでもだいぶ変わるんじゃないかなと思っています。

ボディビルダーの横川さんが証言するように、有酸素運動はカロリーを減らしてしまうということを考えると、体を大きくするためには避けているようですね。
筋トレによる疲労回復の誤解
筋トレ後にクールダウンを行うことで乳酸を除去し、疲労回復につながると考えられていました。
しかし、最近の研究では、疲労は乳酸ではなく水素イオンの蓄積によって引き起こされることが分かり、アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋肉の酸性を低下させる効果は確認されていません。
筋肉痛の軽減は幻想
アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋肉痛や筋損傷マーカーを減少させるという考え方は、長年にわたり広く受け入れられてきました。
しかし、2018年に行われたメタアナリシスによって、この説の根拠が示されていないことが明らかになりました。以下に、関連する情報を詳しく解説します。
2018年のメタアナリシスの結果
研究の概要:2018年にポアティエ大学が実施したメタアナリシスでは、アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋肉痛や筋損傷マーカーに対して、有意な効果を持たないことが示されました。
代替手段:この研究では、筋肉痛や疲労感を改善するための最も効果的な方法として「マッサージ」が挙げられています。
筋肉痛と筋損傷マーカー
- 遅発性筋肉痛(DOMS):運動後に感じる筋肉の痛みで、特に強度の高い運動後に発生。
- 筋損傷マーカー:血液中の特定の酵素やタンパク質が、筋肉の損傷を示す指標として用いられます。
有酸素運動<マッサージ
アクティブ・クールダウンが筋肉痛や筋損傷マーカーを減少させるという従来の常識は、2018年のメタアナリシスによって疑問視されていて、代わりにマッサージなどの他の回復手段が効果的であることが示されています。
この新たな知見は、トレーニング後の回復方法を見直すきっかけとなるでしょう。
この情報は、アクティブ・クールダウンの効果に関する理解を深め、より効果的な回復方法を選択するための参考になると思います。
運動後のケアを見直すことで、より良いパフォーマンスを引き出すことができるかもしれません。
脳疲労の改善も期待できない
高強度トレーニング後には、身体だけでなく脳にも疲労が生じることがありますが、アクティブ・クールダウンがこの中枢性疲労に対して効果的であるという証拠は存在しないのです。
以下に、関連する情報を詳しく解説します。
高強度トレーニングと脳の疲労
- 中枢性疲労:高強度トレーニング後、筋肉の疲労だけでなく、脳の疲労も発生します。
これは、神経活動が筋力の発揮に大きく関与しているためです。 - 影響:中枢性疲労は、注意力や反応速度の低下を引き起こし、トレーニングのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
研究結果
- メタアナリシス:2018年のメタアナリシスでは、アクティブ・クールダウンが筋肉痛や筋損傷マーカーに対して効果がないことが示されました。
- 中枢性疲労への影響:アクティブ・クールダウンが中枢性疲労に対しても効果的であるという証拠はなく、現在のところ期待できないとされています。
有酸素運動 ≠ 脳の疲労
高強度トレーニング後の脳の疲労に対して、アクティブ・クールダウンが効果的であるという証拠はありません。
中枢性疲労を軽減するためには、トレーニング後の回復方法を見直すことで、より良いパフォーマンスを引き出すことができるかもしれませんので、運動後のケアを大切にし、効果的なリカバリー方法を見つけていきましょう。
柔軟性向上の期待も裏切られる
アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋肉の硬さを改善し、関節の可動域を広げるという説には、最近の研究によって否定的な見解が示されています。
特に、アクティブ・クールダウンとストレッチの効果を比較した結果、アクティブ・クールダウンには有意な効果が認められないことが明らかになっています。
研究結果
いくつかの研究では、アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が、筋肉の硬さや関節の可動域を改善するというポジティブな結果は示されていません。
特に、サッカー選手を対象にした研究では、ストレッチによるパッシブ・クールダウンと比較して、アクティブ・クールダウンの効果は有意ではないとされています。
ストレッチとの比較
- ストレッチの効果:ストレッチは筋肉痛を軽減し、可動域を広げるために広く行われていますが、運動の前後に行っても筋肉痛が軽減されないことが報告されています。
- アクティブ・クールダウンの限界: アクティブ・クールダウン(有酸素運動)は、筋肉のグリコーゲンの合成速度においても、パッシブ・クールダウン(ストレッチ)と比較して有意な差がないことが示されています。
クールダウンの必要性
- クールダウンの実施:クールダウンとして軽い運動を長時間行うことは、筋肉内のグリコーゲンの回復を遅らせる可能性がありますが、なるべく高強度のトレーニング後には、素早くグリコーゲンを回復させることがポイント。
- 疲労物質の除去:軽い運動を行うことで、筋肉内の疲労物質(乳酸など)を早期に除去する効果があるとされています。
有酸素運動≠可動域改善
アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋肉の硬さや関節の可動域を改善するという説は、現在の研究によって否定されていて、ストレッチと比較しても有意な効果は認められていないようです。
筋グリコーゲンの合成に影響
アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋グリコーゲンの合成を促進するという考えは、最近の研究によって否定されています。実際には、有酸素運動が筋グリコーゲンの合成を妨げる可能性が指摘されています。
研究結果
高強度トレーニング後の研究では、アクティブ・クールダウン(有酸素運動)を行った場合、筋グリコーゲンの含有量が増加しなかったことが示されていて、パッシブ・クールダウン(ストレッチ)では有意な増加が見られました。
筋グリコーゲン合成への影響
- 合成の妨げ:アクティブ・クールダウン(有酸素運動)が筋グリコーゲンの合成を妨げる可能性があることが、いくつかの研究で報告されています。
特に、高強度トレーニング後に有酸素運動を行った場合、筋グリコーゲンの合成が抑制されることが示されているそうなんです。 - ストレッチとの比較:ストレッチを行った場合には筋グリコーゲンが増加したのに対し、有酸素運動ではその増加が認められなかったという研究結果もあります。
アクティブ・クールダウンの生理的効果
- 心拍数と呼吸数の回復:アクティブ・クールダウン(有酸素運動)には、心拍数や呼吸数を早く正常に戻す効果が期待されています。
サイクリングトレーニング(ロードバイクなど)後の研究では、アクティブ・クールダウンがパッシブ・クールダウンよりも効果的であることが示されています。 - 体温調整:トレーニング後の体温を下げるために発汗が促進され、これもアクティブ・クールダウン(有酸素運動)の一環として重要です。
有酸素運動≠菌グリコーゲン合成促進
アクティブ・クールダウンが筋グリコーゲンの合成を促進するという考えは、現在の研究によって否定。
むしろ、有酸素運動が筋グリコーゲンの合成を妨げる可能性があることが示されています。
心理的ストレスの回復も期待できない
トレーニングによる心理的ストレスの増加や睡眠量の低下に対して、有酸素運動が効果的であるという証拠は見つかっていませんし、トレーニング経験が少ない場合には、逆効果になる可能性も指摘されています。
有酸素運動と心理的ストレス
トレーニング経験が少ない人にとっては、運動が逆にストレスを増加させることがあるとされていて、特に運動に対する身体的・精神的な適応が不十分な場合、過度なトレーニングがストレス反応を引き起こす可能性があると言われているのです。
睡眠と有酸素運動
- 睡眠の質への影響:有酸素運動は一般的に睡眠の質を向上させるとされていますが、トレーニングの強度や時間帯によっては、逆に睡眠を妨げることもあると言われていて、特に就寝前の激しい運動は、睡眠の質を低下させる可能性があります。
- 個人差の重要性:睡眠の質やストレスの感じ方は個人によって異なるため、運動が必ずしも全ての人にとって有益であるとは限りませんし、特に運動習慣がない人は、運動を始める際に注意が必要。
結論
有酸素運動が心理的ストレスや睡眠に与える影響については、効果があるとする意見もありますが、トレーニング経験が少ない場合には逆効果になる可能性があることが示されています。
クールダウンの注意点
ヴァン・ホーレンらの研究によると、アクティブ・クールダウンには乳酸の除去効果が期待できるものの、それ以外の生理的効果は現在のところ確認されていません。
クールダウンを行う際には、以下の3つの注意点を考慮しましょう。
- 低〜中強度で行う:血流を増加させることを目的とし、筋肉損傷を防ぐためにも低〜中強度で行うことが重要。
- 30分以内に留める:筋グリコーゲンの合成を妨げないよう、クールダウンは30分以内に留めましょう。
- 個人に合った方法を選ぶ: プラセボ効果も考慮し、自分に合ったクールダウン方法を見つけることが大切です。
まとめ
筋トレ後の有酸素運動には、これまでの常識が覆る結果が多く報告されています。
ストレッチの方が効果的であることが示唆されていますが、必ずしも有酸素運動が悪いわけではありません。
自分に合った方法を見つけ、効果的なクールダウンを行いましょう。
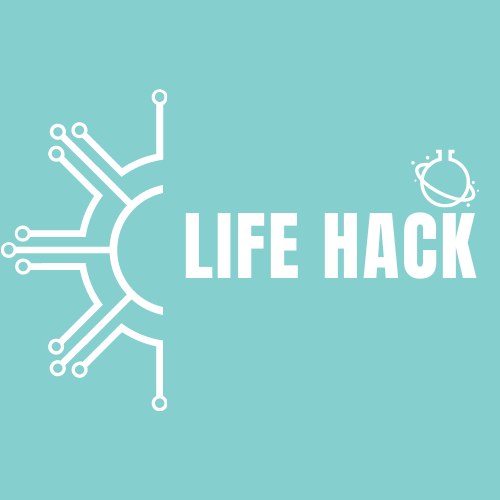




コメント