「筋トレの正しいやり方と信じられていることの大半が、
筋力強化という点では、あまり効率的ではない」
例えば、下記の通り。
「毎日筋トレをしなければならない…」
「筋トレには、時間がかかる…」
「体をいじめないといけない…」
「1日に何セットもやらないといけない…」
「追い込んでこそ、筋トレだ…」
ボディビルダーを目指しているわけでもないのであれば、
体をいじめ抜くハードな筋トレも全く必要としない。
「ライバルよりももっとたくさんやる」という
自分からのハードな筋トレは、身体にとって有害となってしまう。
なぜならば、正しい筋トレは、毎日のようにできないもの。
むやみに時間やセット数をかける筋トレや、身体をいじめ抜く筋トレは正しくない。
正しいのは、週1回程度の各種目はそれぞれ30秒。
やることはそれだけであって、メキメキ筋肉がついてきて、効率的に強くなれる。
また、筋肉強化のために、最も効率のいい強度の運動の目安は、
10回程度やっと挙げられるくらいの負荷で、それをできる限り早くやるということ。
今回の記事では、間違った筋トレをしていないかどうかチェックするために、
一度だけ、記事を通して正しい筋トレを戻せるように、軌道修正していこう。
効率的な筋トレまとめ
❶筋トレは、週に1回、各種目30秒でいい。
❷効果は抜群。ぐんぐんと筋肉がついてくる。
❸かっこよくなる。身体が締まる。
❹健康になる。関節痛などの痛みが取れる。
❺何歳からでも始められる。老化に唯一抵抗することができる。
やっていませんか?非効率な筋トレ方法
低強度の運動習慣での筋トレはNG!
無酸素運動は、筋肉に大きな負荷をかける運動。
フルパワーで高強度の無酸素運動を行うと、
身体が筋肉を大きくしなければ対応できないという状況に置かれます。
この状況に「適応」するために、筋肉が強くなっていく。
ただ、高強度すぎて1RM(1回しか上げれない重量)は意味のない筋トレであるので、
自分が10RM挙げれて、かつスピードのあるものの重量を選ぶのがポイント。
長時間、低いパワーで続けている筋トレはNG!
高強度の運動では、長時間、フルパワーで出し続けることは不可能。
言い換えてみると、長時間も続けられる運動はフルパワーではなく、高強度でもない。
運動強度の低い運動になってしまったら、筋肉を強くする適応を引き起こせないので、
結果的には、筋肉が強くならないという仕組みになります。
強度が落ちれば、有酸素運動となってしまうのです。
有酸素運動は、筋肉強化ではなく、心肺機能に負荷がかかるだけです。
こういった根本的な原理から外れた筋トレは、いかに世間一般から認められていても、
筋力を鍛えるという点では、効率的な運動とはなり得ないものです。
フルパワーが出せる30秒=1セットのみで十分ということです。
筋トレを毎日やるのはNG!
筋トレというものは、『高強度な運動習慣に筋肉を適応させること』
高強度な運動というものは、全力ダッシュを自分でできる限界まで継続するような運動。
どんなに頑張っても、せいぜい30秒が限界。
1日に何時間もできる、しかも毎日のように筋トレができるというものは、
それ自体が高強度ではなく、中強度か低強度の運動になってしまっているだけです。
中程度や低強度の運動をやっていても、筋トレにはならない。
逆に高強度の筋トレを毎日やるのは、危険であって、効果が薄い筋トレ方法の一つ。
最大重量にこだわった1RMのみの筋トレはNG!
筋トレそのものを、重量上げであるという勘違いが多いのげ現実。
1RMは、どんなにフルパワーで1回しか持ち上げれない重量という意味です。
その1RMで最高重量を目指すのが、筋トレであるのか?と言われると、間違い。
ポイントとしては、『パワー=かかる力 × 速さ』
重さだけではなく、それをもち上げるための速さが問題であるということなんです。
1RMでは、挙げるのが精一杯ですので、速さとしては遅くなってしまいます。
その運動として得られるパワーは、最大ではなく、筋トレ的には効果のない筋トレ。
正しい筋トレとしては、ある程度重量を落として、できるだけ早く挙げれる重量で、
筋トレを続けられるまで行うことがポイント。
低重量筋トレから始めるのはNG!
運動を始めた後、最大パワーとして出せるのは、どのレップであるのか?
と言われると、最初の数回にしかパワーは発揮しないものです。
同じ重量を挙げ続けているのであれば、必要な力というものは変わりはありません。
なので、最初のもっとも速いスピードで挙げれるときこそ、最大のパワーが発揮されるのです。
例えばベンチプレスであると、40kg→45kg→55kg(最大)ということではなく、
最初から55kgを扱って、挙げきれないぐらいのところまで挙げていくということ。
出来る限りハイパワーな状態で出し切って、
最終的に1回も挙げれない状態まで持っていく。
そうすることによって、高強度の運動が筋肉に対する適応刺激になっていき、
はじめて筋肉と筋力が増強されるようになっていきます。
最初から最大パワーを出し損なってしまって、ダラダラ と続けてしまった場合。
その後に追い込んでさらに最大パワーを出せるのか?と言われると、それは不可能であるのです。
次にまた最大パワーを出せるのは、2日以上かかってしまいます。
筋トレ効果と最大限にと考えるのであれば、最初が肝心なんです。
無理やり筋損傷で、超回復を狙うのはNG!
筋肉に負荷を与えて筋肉を破壊すると、休息後に『超回復』が起こって、
筋肉が増強されるという、超回復理論ということ。
だが、無理やり筋繊維を壊すものではありません。
重要視とするならば、筋繊維をいかに損傷させるのではなく、
筋繊維にどのような動きをすれば、1番強くなれる「適応」を筋肉から引き出すこと。
自分がもつフルパワーを一気に出しつつ、それを出来るだけ長く続けること。
1セット(10レップ)の30秒で終わってしまうが、この運動こそが筋トレの根幹。
変に100kgのバーベルスクワットを3セットやって追い込むようなことして、
筋肉を損傷するまで追い込んでいく必要は、一切必要としないということです。
様々なセット法をやる筋トレはNG
最もシンプルな方法として、ある筋トレを10レップの3セット。
さらには、1セットは強めにやって、次から弱めていくドロップセットや、2種ごとを連続交互に行っていくスーパーセット、他書多様セットを組み合わせてやるジャイアントセット。
筋トレ業界では、こんなふうにたくさんの筋トレ方法を編み出しています。
だが、人それぞれの個人差があるので、効果があるかどうかは一概には言えません。
だが、最も高強度な運動をできなくなるまで継続をすると、筋肉にさらにパワーアップしようという適応が起こる。というのが、筋トレにおいて正しいものです。
全力出した次のセットは、最大パワーを発揮した運動はできない。
何セットやっても、セット内容を工夫しても、筋肉のパワーアップさせる運動になり得ない。
だからこそ、1種目につき1セット。
マンネリ打破のために種目を変えたりするのNG!
日々の習慣の積み重ねで体が変わっていくのです。
慣れる=筋肉に適応が起こって、最大パワーが出せる運動をするのが最も効果的。
せっかく最大限のパワーが出せる筋トレ種目だったのにも関わらず、違う種目に手を出してしまってしまうと、また1からパワーをつけ直しの始まりで時間がもったいないのです。
筋トレで生じる効果は適応(慣れる)です。
それを引き起こすには、習慣化が必要なので、毎回違うことをする必要はありません。
ピンポイントを狙った筋トレはNG!
私たちが行なっている筋トレは、大きく分けると2つあります。
・単関節運動
・多関節運動
単関節運動…1つの関節が関与した運動
多関節運動…2つ以上の複数の関節が関与する運動
(例)単関節運動は、ダンベルカールのような肘関節の屈曲・伸展動作。
(例)多関節運動は、ベンチプレスのように、胸や腕、背中へと2つ以上の関節動作。
単関節運動であると、自然に軽重量での筋トレになってしまうので、
本当に筋肥大しているかどうかを疑うべきであるのです。
逆に多関節運動であると、多くの部位を一気に引き出して大きな力を発揮します。
なので、多くの筋肉部位を鍛えられるということになるのです。
適応としての筋力向上を狙うのであれば、フルパワーで多くの関節を使う、
多関節運動で、筋トレを行った方が最も効果的であるということです。
一般的には、高重量を扱える人の方が体格が大きいんです。
パンプアップさせようとする筋トレはNG!
筋トレをしていくと、自然とパンプアップするのは皆さん同じこと。
しかし、パンプアップしても筋肉が強く、大きくなるわけではないのです。
筋肉を大きくさせたいのであれば、
筋肉が強くなる適応刺激を与えないといけないのです。
ちなみにパンプアップする正体としては、
水が溜まって膨れ上がっていると言われています。
しばらくすると元に戻るというように、水が溜まって膨れ上がっているからこそ、
パンプアップという現象が見られているだけです。
筋肉そのものが、大きくなるということではないのです。
呼吸法にこだわって筋トレはNG!
筋トレにおいて、呼吸法にこだわっている人も多数います。
「ここで吸って、ここのタイミングで吐いて」という感じで、指導が細かい。
でも、息を止めないのが1番。
息を止めてしまと、筋トレそのものが続けられません。
息が上がって、苦しい思いをするだけ。
普通に「ハー!ふー!」って思う存分に息をすればいいのです。
呼吸そのものには、高強度の運動を行う上では、
重要な要素に入っているということではないのです。
加圧トレーニングでの筋トレはNG!
昔に流行っていた『加圧トレーニング』そのものは、腕や足のつけ根に専用のベルトで
圧力をかけて、血流を制限してトレーニングを行うという方法。
効果としては、低負荷・短時間で効果を出せるということ。
それをすることによって、低負荷でパンプ感を得られるというもの。
でも冷静に考えてみて下さい。
加圧トレで筋肉量が増えたとして、それが本当に筋力を発揮する筋肉が増えたのか?
疲労物質(老廃物)がたまっても、動ける適応で何かが肥大したのか?
そういった理由が不明でありながらも、加圧トレーニングは意味がないもの。
しっかりと高強度な運動をすれば、筋トレ効果が出るもの。
わざわざ血流を止めてまで、苦痛な運動しなければならないのだろうか?
HIITで筋肥大を狙おうとする筋トレはNG!
『HIIT』は、Hight-Intensity Interval Treaningの略称。
「高強度インターバルトレーニング」と訳されています。
開発者の立命館大学スポーツ健康科学部の田畑泉 教授の名前からとって、
『タバタトレーニング』と呼ばれるようになってきました。
自重で高強度、かつ短時間の運動
ごく短い休憩を挟みながら、繰り返すというトレーニング方法。
しかし、フルパワー運動にはならないので、筋トレ効果としては認められない。
パワーを得るためには、重量のあるものを早く動かし、
筋肉にこの状態に対する『適応』を起こさせる必要というのがあるのです。
筋肉に適応が起こるようなトレーニングを、短い休憩をとるだけで、
続けて行うということなど、不可能であるのです。
逆に筋肉に適応が起こらないような軽い負荷であると、トレーニング時間は長くなります。
長くなればなるほど、無酸素運動から有酸素運動に移行してしまいます。
そうなってくると筋肉強化ではなく、心肺強化ということになります。
多関節運動の6つの筋トレ
・脚で蹴る、押す(スクワット、レッグプレスなど)
・脚を挙げる、引く(負荷コントロール可能である腹筋運動)
・手で前へ押す(ベンチプレス、チェストプレスマシンなど)
・手で上へ押す(ショルダープレスなど)
・手で上から引く(ラットプルダウンなど)
全身で鍛える意味で、単関節運動よりも多関節運動の方がよりフルパワーを発揮。
鍛えられる部位が多いので、単関節運動よりも効率的であるのです。
各種目の筋トレのポイント
①挙げる時は、全力を出して、できるだけ速く動かす。
(重量を挙げるとき:ポジティブ)
②戻す時は、力を抜かずにゆっくり戻す。
(重量を下げるとき:ネガティブ)
③途中で休まない、力を入れ続ける。
(楽を求めない。力が入った状態をキープして筋トレする)
筋トレは週1回、各部位1種目1セットでOK
筋トレをどのくらいの負荷、何回、頻度で行うのか?ということ。
重量が大きすぎると、1RMのような重量では速く動かすのは不可能であること。
逆に速く動かせるといっても、20回〜30回もできてしまうようでは、
筋トレにおいて、適応されてないということになるので、意味がありません。
ポイントとしては、自分が速く挙げれていると思える、
最も重い負荷を選択するのがいいのです。
だいたい10回(レップ)くらい、やっとできるくらいの負荷でやっていきましょう。
変なことを考えずに、最初から全力でやっていくこと。
フルパワーを出すことに意識して、筋トレに集中していきましょう。
途中で休んでしまっては、元も子もありません。
そのときの運動は、筋トレという効果はありません。
一気に高強度の運動を与えると、筋肉はもっと強くなろうとするのです。
1種目1セット、1週間に1回で十分。
超強度の運動をしたら、体を休ませることが必要。
1週間に2回以上はやらないことがポイントになってきます。
3回以上やっても問題がないという場合は、そもそも1回の強度が不足しているだけ。
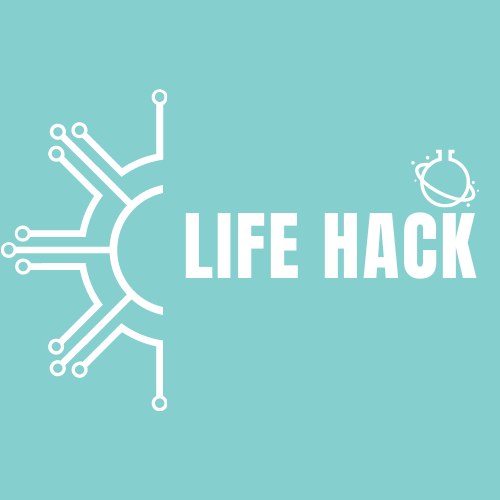
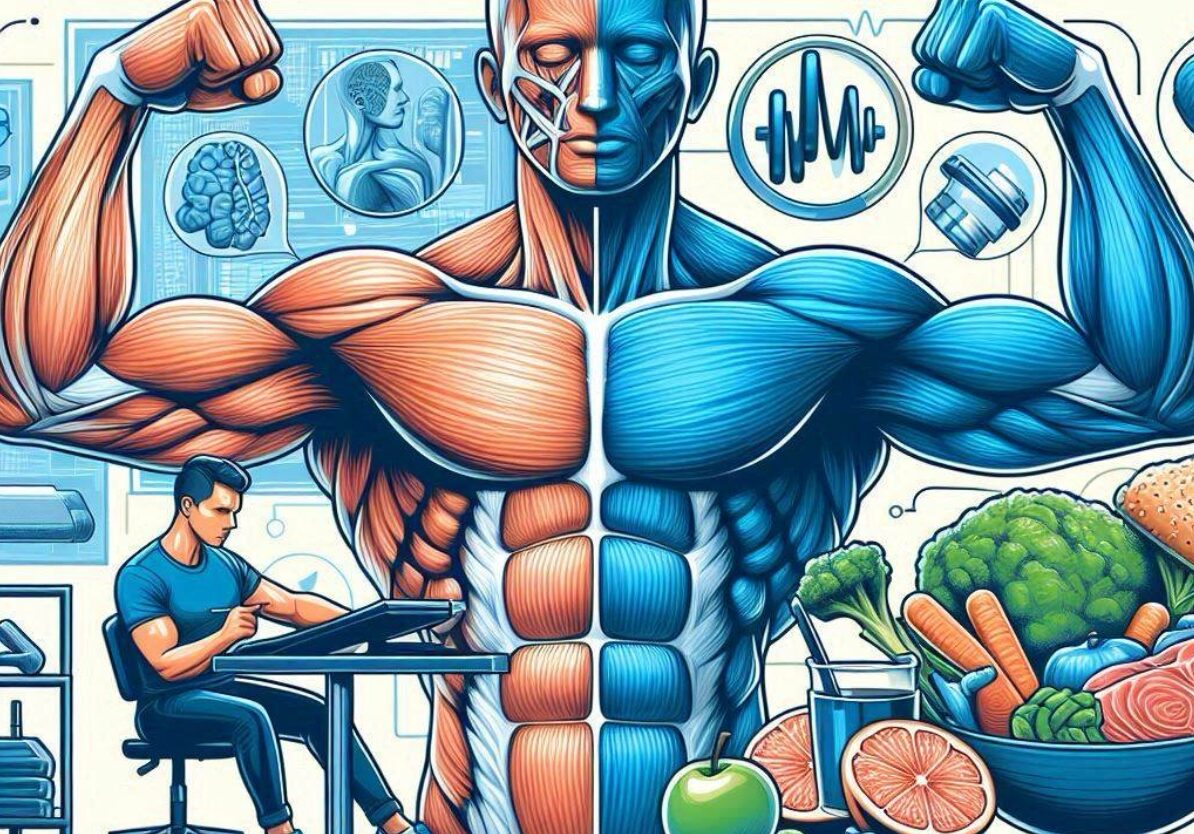


コメント